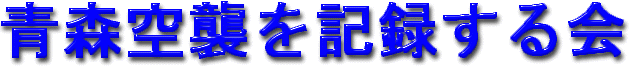火輪の地獄に
小林妙子
昭和二十年七月二十八日。警戒警報のサイレンが寝入りばな、夢うつつの中に流れる。連日の暑さと農作業の疲れで起きる気力もない。私はその時中学校三年生(滿十五歳)であった。父の声がいつもより大きく「起きろ」と、私をゆさぶっている。姉はすでにきちんと身支度を整えている。
「青森市民のみなさん、がんばって。がんばって」
と、言うラジオのアナウンサーの甲高い声ではっきり目がさめた。身支度もそこそこに外へ飛び出す。と、同時に投下された照明弾。今まで見たこともない花火のような美しさにみとれ、一瞬私達父姉はその照明弾に合掌していた。なぜだか解らないが何か祈らずにいられなかったのだと思う。
焼夷弾が投下され、市街の西と東からほとんど同時に火の手があがり、瞬く間に市街全体が火の輪につつまれてしまった。ひっきりなしに投下される焼夷弾。直撃されて目の前で死んでゆくもの。火だるまになって川に飛び込むもの。まさに地獄図さながらである。敵はさんざんその情景を楽しみ、やがて悠々と引き揚げていった。
空襲警報解除になってもなお、燃えつづけ、人々の必死の防火によってようやく火の手が鎮まり、白々と地獄の夜が明けた。ホッと人心地がついたときは父も姉も居ず、私の周りは知らぬ人ばかり。父や姉は? ともかく家に帰らねばと燃えくすぶる街を目指して、ごろごろ転がっている死骸や異臭にむせながら黙々とひとり家路をたどった。
家に着いたのは二十九日の昼頃だった。幸い家は焼けていなかった。たった一夜なのに十数年振りの再会のような気がした。焼け残った家を解放して、ありったけの米を炊き、勝つための明日を目指して炊き出しの準備にかかった。九死に一生を得たいのち。戦争のむごさをまざまざと体験し、戦争のない世界を祈りながら生きてきた。が、別な意味での戦争が繰り広げられているように思う。本当の平和とは何なのか。停年近い歳になってもまだ迷いの道をさまよっている昨今である。
次代への証言第十集